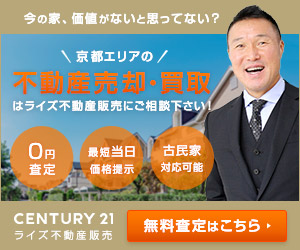不動産売却に伴う仲介手数料の仕訳方法について悩んでいませんか?
不動産売却の仲介手数料は、通常「支払手数料」という勘定科目で処理されます。
適切な勘定科目への振り分けは、確定申告や決算処理をスムーズに進めるために欠かせません。
本記事では、個人事業主と法人それぞれの仕訳例をわかりやすく解説します。
また、仲介手数料の計算方法や注意点についても詳しく取り上げます。
不動産売却が初めての方でも理解しやすい内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
不動産売却に関する仕訳の基本

不動産売却時の収入や経費を正しく仕訳することは、確定申告や法人税の計算において非常に重要です。
売却価格から経費を差し引いて計算した利益が課税対象となります。
不動産売却による収益は、法人であれば「土地売却益」や「建物売却益」、個人事業主であれば「譲渡所得」として扱います。
売却時に仕訳すべき主な項目には、売却益や手数料、登記費用、印紙税などがあります。
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 支払手数料 |
| 登記費用 | 支払手数料またはその他経費 |
| 印紙税 | 租税公課 |
これらを適切に処理することで、税金を正確に計算し、不要なトラブルを回避できます。
仲介手数料の勘定科目とは?

仲介手数料を正しく仕訳することで、確定申告や決算処理がスムーズになります。
個人事業主と法人では、扱いが若干異なるため、それぞれの仕訳例を確認しておきましょう。
不動産売却を行なった際に支払った仲介手数料の勘定科目は、個人事業主と法人どちらも、「支払手数料」です。
◆仲介手数料のみの記載例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 支払手数料 | 100万円 | 普通預金 | 100万円 |
基本はこの形で、借方と貸方の金額が一致するように記載する必要があります。
ただ、売却時に得た利益や手付金などを含めると、記載方法は個人事業主と法人とで若干異なる点に注意が必要です。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、仲介手数料は「支払手数料」として計上します。
これにより、課税所得を減らすことが可能です。また、不動産の用途が事業用である場合、経費計上が認められます。
ただし、プライベート用が含まれる場合には、事業用部分のみ計上することが求められます。
◆個人事業主の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 3760万円 | 土地 | 800万円 |
| 事業主借 | 500万円 | ||
| 建物 | 1500万円 | ||
| 事業主借 | 800万円 | ||
| 前受金 | 200万円 | 仮受消費税 | 360万円 |
| 支払手数料 | 100万円 | 普通預金 | 100万円 |
割合計算が必要なケースでは、不動産の使用状況を明確に記録しておきましょう。
法人の場合
法人の場合、仲介手数料は主に「支払手数料」や「営業外費用」に計上されます。
不動産売却が事業活動の一環である場合には「支払手数料」として記録することが一般的です。
一方で、事業外の収益に関わる売却であれば「営業外費用」として処理します。
◆法人の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 3760万円 | 土地 | 800万円 |
| 固定資産売却益 | 500万円 | ||
| 建物 | 1500万円 | ||
| 固定資産売却益 | 800万円 | ||
| 前受金 | 200万円 | 仮受消費税 | 360万円 |
| 支払手数料 | 100万円 | 普通預金 | 100万円 |
法人税計算の基礎となるため、正確な処理が求められるため、税理士への相談もおすすめです。
仲介手数料の計算方法とは

勘定科目がわかったところで、仲介手数料(支払手数料)の項目に実際に書く金額を計算してみましょう。
不動産の売却時、土地の売却に関しては、消費税は非課税です。
しかし、建物の場合は売却時に消費税がかかり、仲介手数料も同様に消費税が発生します。
仲介手数料は、不動産会社に支払う成果報酬であり、宅地建物取引業法によって上限が定められています。
計算式は下記の通りです。
◆計算式
売買価格 × 3% + 60,000円 + 消費税
| 不動産の売買価格(税抜) | 上限額 |
|---|---|
| 800万円未満の場合 | 30万円+消費税 |
| 800万円以上の場合 | (売買価格の3%+6万円)+消費税 |
よほどボロボロで需要がない不動産でなければ、400万円を下回ることはほとんどありません。
そのため、基本的には上記表の、3行目の計算式を使用することになるでしょう。
例えば、3,000万円の物件を売却する場合、手数料は以下の通り計算されます。
3,000万円 × 3% + 60,000円 = 960,000円
消費税10%を加えると、1,056,000円となります。
法律で定められた上限額を超える手数料請求は違法ですので、契約時には明細書を確認してください。
また、消費税が別途加算される点に注意しましょう。
仲介手数料に関する注意点

不動産売却時に発生する仲介手数料は、会計処理や税務上でいくつかの注意点があります。
これらを事前に把握しておくことで、余計なトラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
特に、仲介手数料は不動産取引の中で重要な経費として扱われるため、その取り扱いについて正確に理解することが求められます。
仲介手数料に関する最大の注意点は、税務上の扱いが売却時と購入時で異なる点です。
また、手数料に消費税が加算されるため、正しい金額を記録することも重要です。
以下では、特に間違いやすい2つのポイントについて詳しく説明します。
仲介手数料は基本的に非課税にならない
仲介手数料には消費税が課されるのが一般的です。
不動産取引そのものが非課税の場合でも、仲介手数料が非課税になることはほとんどありません。
この点を誤解すると、会計処理や税務申告でミスをする可能性があるため、注意が必要です。
極めて限定的な場合を除き、仲介手数料は課税対象です。
具体的な例として、公益法人など特定の免税事業者が絡む取引では非課税となることもありますが、一般的な取引では該当しません。
- 仲介業者からの請求書に記載される消費税額を必ず確認する
- 消費税が正確に計算されていない場合は修正を依頼する
- 消費税額を含めた合計金額を仕訳に反映する。
正確な記録を行うことで、税務調査の際にも説明がしやすくなります。特に消費税の金額を把握することは重要です。
不動産の購入時には経費計上が認められない
不動産を購入した際に支払う仲介手数料は、経費として計上することができません。
これは、購入時の仲介手数料が不動産の取得価額に含まれるためです。
一方で、不動産を売却した際には必要経費として計上できます。この違いを理解し、適切に処理することが重要です。
購入時には、仲介手数料は不動産の取得価額に含めて記録します。
これは、取得価額が将来的に売却益の計算基準となるためです。
そのため、購入時の領収書や契約書をしっかり保管しておく必要があります。
売却時には、仲介手数料を必要経費として計上することで、課税所得を減らすことが可能です。
購入時に記録された取得価額と売却時の手数料を合わせて正確に計上しましょう。
購入時と売却時で経費計上のルールが異なるため、それぞれの記録方法を正しく理解することが大切です。
誤った処理をすると、後で修正が必要になるだけでなく、税務署から指摘を受けるリスクもあります。
まとめ
不動産売却における仲介手数料の仕訳は、正確さが求められます。個人事業主と法人で若干の違いがありますが、基本的には「支払手数料」として記録することが一般的です。
また、手数料計算の方法や消費税の取り扱いについても十分理解しておくことが大切です。
税務処理を正確に行うためには、会計ソフトや専門家のサポートを活用するのが効果的です。
不動産取引をスムーズに進めるためにも、正確な記録を心がけましょう。