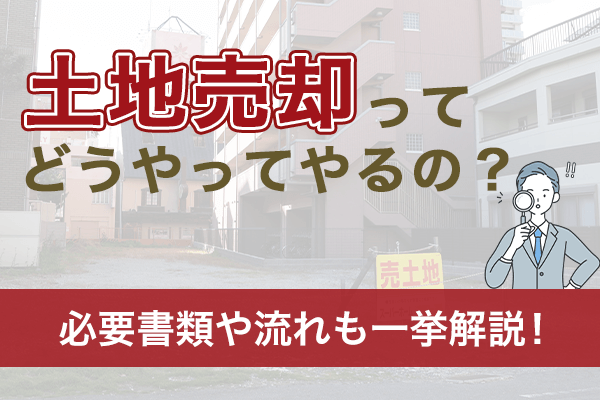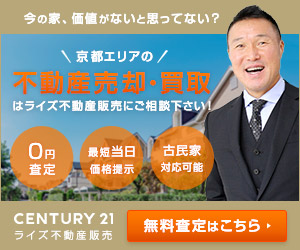「土地を売却したいけど、どうやって売ればいいか分からない」
「不動産仲介業者に相談したいけど、いきなり連絡するのは不安」
土地売却を考えてはいるものの、最初の一歩が踏み出せずに悩んでいる方は多いです。
不動産仲介業者に依頼することで、相場の調査や売却戦略の立案、買主との交渉、契約手続き、税務のアドバイスまで、専門的なサポートを受けることができます。
そんな悩みを抱える方に向けて、この記事では土地売却の基礎知識から相談先、必要書類や流れ、税金や注意点までを丁寧に解説します。
相談先の選び方や必要書類、具体的な売却の流れ、気をつけたいリスクや税金の基礎、さらには高く売るためのコツまで、まとめてご紹介。
読み終わるころには、「何をすればいいか」「どこに相談すればいいか」が明確になり、不安を取り除いた状態で土地を売却することができます。
土地売却を成功させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
土地を売却する前に知っておくべきこと
土地を売ると決めたら、すぐに売却活動に入るのではなく、まずは基本的な知識と準備が重要です。
誰に相談すべきか、どんな書類が必要か、どんな費用がかかるのかの理解が、スムーズな売却につながります。
ここでは、売却に向けて最初に知っておくべき3つのポイントをわかりやすく解説します。
- 土地を売りたいときは不動産仲介業者に相談する
- 名義や境界についての必要書類を確認する
- 土地売却には費用や税金が発生することを理解する
土地を売りたいときは不動産仲介業者に相談する
土地を売却したいと思ったとき、最も多くの方が迷うのが「まず誰に相談するべきか」という点です。
不動産仲介業者は土地の相場を把握しており、売却活動に必要な広告戦略・契約手続き・法的書類の取り扱いまで一貫してサポートしてくれます。
一括査定サイトを活用すれば、複数の不動産仲介業者から無料で査定を受けられ、相場観を掴むのにも有効です。
名義や境界についての必要書類を確認する
土地を売るには、法律上の「所有者」が明確であることが大前提です。
登記簿上の名義が自分の名前になっていなければ、売却はできません。
特に相続した土地や共有名義の土地は、事前に相続登記や同意手続きが必要です。
また、隣地との境界が不明確な土地はトラブルの原因になります。
必要な書類としては以下が代表的です。
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 公図・測量図
- 固定資産税の納税通知書
- 印鑑証明書、本人確認書類
書類の不備により、売却が遅れたり買主が不安を抱くケースもあるため、事前準備はしっかりと行いましょう。
土地売却には費用や税金が発生することを理解する
土地を売ることで得られた金額がそのまま収入になるわけではありません。
売却には仲介手数料・登記費用・印紙税・譲渡所得税などのコストがかかります。
具体的には次のような費用が想定されます
| 費用項目 | 概要 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円+消費税(※上限あり。不動産仲介業者に支払う手数料) |
| 印紙税 | 売買契約書に応じて課税(例:1,000万円超で1万円) |
| 登記費用 | 登録免許税と司法書士への報酬(登記手続きに必要) |
| 譲渡所得税 | 売却益が出た場合に課税される所得税・住民税(所有年数や特例により変動) |
特に譲渡所得税は、取得費・売却経費・所有期間によって税率や控除が変わるため、事前のシミュレーションが必要です。
不明点がある場合は、不動産仲介業者だけでなく税理士への相談も視野に入れましょう。
土地売却の流れをステップごとに確認しよう
土地売却には明確な「手順」があります。
どのステップも飛ばすことはできず、ひとつずつ丁寧に進めましょう。
ここでは、書類の準備から査定依頼、売買契約、最終的な引渡しまで、実際の流れを時系列でわかりやすく紹介します。
- 土地売却に必要な書類を準備しておく
- 複数の不動産仲介業者に査定を依頼する
- 媒介契約を結び売却活動をスタートする
- 購入希望者と条件交渉し売買契約を締結する
- 決済と引渡し後は確定申告が必要になる
土地売却に必要な書類を準備しておく
土地の売却をスムーズに進めるには、必要書類の準備が欠かせません。
書類が不備だと売却活動が開始できなかったり、契約直前で取引が中断されることもあるため、早めに揃えておきましょう。
代表的な書類は以下の通りです。
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 公図・測量図(境界を確認するため)
- 固定資産税納税通知書
- 本人確認書類・印鑑証明書
- 建物がある場合は建築確認済証や検査済証
土地売却は所有者の状況や土地の用途によって若干変わるため、事前に不動産仲介業者に確認することをおすすめします。
相続や共有名義の場合はさらに追加の書類が必要になりますので、準備には余裕を持ちましょう。
複数の不動産仲介業者に査定を依頼する
土地をいくらで売れるのかを知るために、最初に行うのが査定です。
ただし、1社だけの査定では適正価格かどうか判断しづらいため、必ず複数社に依頼して比較するのが鉄則です。
査定には「机上査定(簡易見積もり)」と「訪問査定(現地調査)」の2種類があります。
机上査定は早い反面、土地の現況や接道状況などが反映されないため、本格的に売却する際は訪問査定が必須です。
一括査定サイトを利用すれば、複数社の査定結果を簡単に比較できます。
媒介契約を結び売却活動をスタートする
不動産仲介業者を選定したら、次に「媒介契約」を結びます。
媒介契約は、不動産仲介業者に正式に売却活動を依頼するための契約で、売主と不動産仲介業者の間のルールを定めるものです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 1社のみ依頼・自己発見取引不可・週1報告義務あり |
| 専任媒介契約 | 1社のみ依頼・自己発見取引可能・2週間に1回の報告義務 |
| 一般媒介契約 | 複数社へ依頼可能・報告義務なし |
売却を急ぐ場合は、営業力のある会社と専属専任媒介契約を結ぶのが効率的です。
媒介契約後はすぐに販売活動がスタートし、ポータルサイトへの掲載やチラシ配布、顧客への紹介などが行われます。
購入希望者と条件交渉し売買契約を締結する
販売活動を通じて購入希望者が現れると、価格や引渡し時期、設備の有無などについて交渉が始まります。
条件がまとまれば、いよいよ「不動産売買契約」の締結に進みます。
契約では、売買価格、手付金、引渡日、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の範囲などが記載されます。
重要事項説明は宅地建物取引士から買主に行われ、トラブル防止のために非常に重要な手続きです。
この時点で買主から「手付金(売買価格の5~10%程度)」が支払われ、契約は法的に成立します。
契約条項には専門用語も多く含まれるため、少しでも不明な点があれば遠慮せず質問しましょう。
決済と引渡し後は確定申告が必要になる
売買契約後、残代金の支払い・所有権移転登記・鍵の引渡しなどを行う「決済日」が到来します。
これにて実質的な売却は完了します。
ただし、売却益が出た場合には、翌年2月〜3月の確定申告期間に「譲渡所得」の申告が必要です。
そのため、必要書類(取得時の契約書や領収書など)をきちんと保管しておくことが重要です。
税金の種類や計算方法に不安がある場合は、税理士への相談も視野に入れましょう。
土地売却で注意すべきリスクと対策
土地の売却にはさまざまな落とし穴が潜んでいます。
境界トラブルや名義の問題、契約後の責任など、予期せぬ事態に備えることが不可欠です。
この章では、土地売却でありがちなリスクを事例ベースで取り上げながら、回避するための具体的な対策を解説します。
- 測量や境界確定を怠るとトラブルになりやすい
- 相続土地や共有名義の売却は手続きが複雑になる
- 契約不適合責任の内容は事前に確認しておく
- 借地や農地など特殊な土地は制限があるので注意する
- 売却スケジュールには余裕を持って準備をする
測量や境界確定を怠るとトラブルになりやすい
土地の境界が曖昧な状態で売却を進めると、後々近隣トラブルや契約解除の原因になりかねません。
とくに買主は、正確な土地面積や隣接地との境界が明確であることを重視するため、測量を怠ると売却価格の低下にもつながります。
境界が未確定の場合は、隣地所有者と立会いのうえ、境界確認書の締結や境界杭の設置を行いましょう。費用はかかりますが、売却後の安心感につながります。
国土交通省のガイドラインでも「不動産取引前の境界確認」は推奨されており、買主・売主ともに後悔しないための基本対策です。
参考:国土交通省│所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
相続土地や共有名義の売却は手続きが複雑になる
相続した土地や複数人で所有する土地(共有名義)を売却する場合、通常よりも多くの法的手続きと関係者の同意が求められます。
相続登記が未了の場合は、売却前に法務局で登記を行う必要があります。
相続登記には戸籍謄本・遺産分割協議書などが必要で、時間がかかる場合もあります。
また、共有名義の場合は、共有者全員の売却同意がないと取引が成立しないため、連絡・書類収集に手間がかかります。
売却のタイミングに余裕がないと対応しきれないこともあるため、該当する方は早めに司法書士や不動産仲介業者に相談しましょう。
参考:横浜地方法務局│長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について
契約不適合責任の内容は事前に確認しておく
売主には、契約後に発覚した欠陥について対応する「契約不適合責任」が課されます。
契約不適合責任は、かつての「瑕疵担保責任」に代わって2020年の民法改正で導入された制度です。
たとえば「雨水が地盤に浸透しやすい」「越境があった」などの情報を事前に伝えていなかった場合、損害賠償や契約解除の対象になることがあります。
そのため、不安がある場合は契約書にて明示し、事実を共有しておくことが大切です。
不動産仲介業者はこうした内容を契約時に「重要事項説明書」に落とし込みますが、売主側の説明責任も明確に存在することを理解しておきましょう。
借地や農地など特殊な土地は制限があるので注意する
借地権付きの土地、農地、山林、または賃貸中の土地など、特殊用途の土地には法律的な制限や申請手続きが必要になります。
たとえば農地は「農地法」に基づいて、農業委員会の許可がなければ売買ができません。
また、借地権や賃借人がいる土地は「借地借家法」の制限を受け、所有者の自由な売却が難しくなる場合もあります。
こうした土地の売却は、一般的な住宅用地よりも専門性の高い不動産仲介業者を選ぶ必要があるため、事前にその土地の状況を確認し、扱いに慣れた会社へ相談することがリスク回避につながります。
売却スケジュールには余裕を持って準備をする
土地売却には、境界確認・書類準備・査定・買主探し・契約・登記・確定申告など、複数の工程があります。
土地売却を1〜2ヶ月で終わらせるのは難しく、最低でも3ヶ月、場合によっては半年以上かかることもあります。
売却を急ぐと、価格交渉で不利になったり、売主側の準備不足が原因で買主が離れてしまうこともあります。
特に「相続が絡んでいる」「遠方の土地を売る」などのケースでは、手続きの遅延が発生しやすいため、時間的余裕を持って計画的に進めることが望ましいです。
土地売却にかかる税金とは?計算方法も合わせて紹介
土地を売却したときに得られる利益(=譲渡所得)には、所得税・住民税などの税金が課されます。
この譲渡所得は、給与や事業所得などとは別に計算される「分離課税」と呼ばれる仕組みで課税されます。
まず、課税の対象となる金額は、以下のように計算されます。
この「課税譲渡所得金額」に、一定の税率をかけて納める税額を算出します。
税率は「所有期間が5年を超えているかどうか」で変わります。
以下の表をご覧ください。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 (5年を超える) | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 (5年以下) | 30% | 9% |
また、復興特別所得税として、所得税額の2.1%が上乗せされます。たとえば長期譲渡所得の場合は、所得税15%に2.1%を加えた合計20.315%が実質的な税率になります。
このように、土地売却には見えにくい税負担があるため、売却益のある方は事前にシミュレーションを行い、必要に応じて税理士や不動産仲介業者に相談しておくことが重要です。
ここでは、土地売却するときに発生する費用を紹介します。
- 印紙税
- 譲渡所得
- 登録免許税・司法書士報酬
- 仲介手数料
それぞれについて詳しく解説していきます。
印紙税は契約金額に応じた納税を行う
土地売却時に取り交わす「売買契約書」には、契約金額に応じた印紙税を納める必要があります。
印紙税は、契約書そのものに「収入印紙」を貼付することで納税する形となります。
印紙税の金額は以下のように契約額によって異なります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
この印紙代は通常、契約書を保管する側が負担します。
1通を売主・買主で1通ずつ作成する場合、それぞれが自分の控えに収入印紙を貼ることが原則です。
譲渡所得税は売却益が出たときに発生する税金
土地を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」が課されます。
譲渡所得は売却で得た利益=譲渡所得に対してかかる税金で、所得税・住民税・復興特別所得税の合算となります。
計算式は以下のとおりです。
譲渡所得にかかる税率は、所有期間によって異なります。
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 (5年超) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 (5年以下) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
特例控除や軽減税率制度が適用されると、税額は大きく減少する可能性があります。
登録免許税と司法書士報酬は登記手続きで発生する費用
土地の売却が完了した際には、所有権移転登記を行う必要があります。
その際に発生するのが「登録免許税」と「司法書士報酬」です。
登録免許税は、登記手続きに対して国に支払う税金で、買主が負担する場合が一般的です。
ただし、契約内容によっては売主負担とされることもあるため、契約前に確認しましょう。
登録免許税の計算は以下の通りです。
一方で登記手続きを代理で行う司法書士には報酬として、3万円~10万円程度発生します。
そのため、登記費用の負担区分や金額については、売買契約の前に不動産仲介業者や司法書士に確認しておくことが大切です。
仲介手数料は不動産仲介業者に支払う成功報酬
土地の売却を不動産仲介業者に依頼した場合、売却が成立したタイミングで「仲介手数料」が発生します。
仲介手数料は、不動産仲介業者が買主を見つけ、売買契約を成立させたことに対する成功報酬です。
手数料の上限は法律で定められています。
また、センチュリー21ライズ不動産販売では、以下の内容で金額が設定されています。
| 不動産の売買価格(税抜) | 上限額 |
|---|---|
| 800万円未満の場合 | 30万円+消費税 |
| 800万円以上の場合 | (売買価格の3%+6万円)+消費税 |
契約時に報酬額や支払時期は媒介契約書で明示されるため、依頼前にしっかりと内容を確認しましょう。
相続や古家付き土地は特例で税金を軽減できる
一定の条件を満たすと、譲渡所得税を軽減・免除できる制度があります。
代表的なものは以下の2つです。
かつて自宅として使っていた土地・建物の売却時に、最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる制度。
対象:いずれかに当てはまる人
- 売却した不動産が自分自身が住んでいた家屋(居住用財産)であること
- 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
- 他人に貸していないこと(賃貸にしていると適用外)
- 売却した不動産の所有者が本人または同一生計の配偶者・親族であること
- 親族や同居していた人などへの売却でないこと
- 譲渡先が法人でなく、関係会社や親族が実質的に経営する法人でもないこと
- すでにこの特例を使ってから2年を経過していない場合は対象外
補足ポイント
- 建物付きの場合:建物と土地が共に居住用であること
- 更地の場合:取り壊した後でも、住んでいた建物の敷地であればOK(ただし取り壊し後1年以内+貸していない)
一定の要件を満たす相続空き家を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除が受けられる制度。
対象:3つの要件全てに当てはまる人
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
補足ポイント
- 売却できるのは「被相続人が住んでいた家屋」または「その敷地」
- 相続後、空き家のままでもOK(ただし賃貸に出すと適用外)
- 解体した場合でも、取り壊し日から1年以内に売却する必要がある
売却が遅れてしまうと、控除が受けられなくなる可能性があるため注意しましょう。
土地を高く売るためにできること
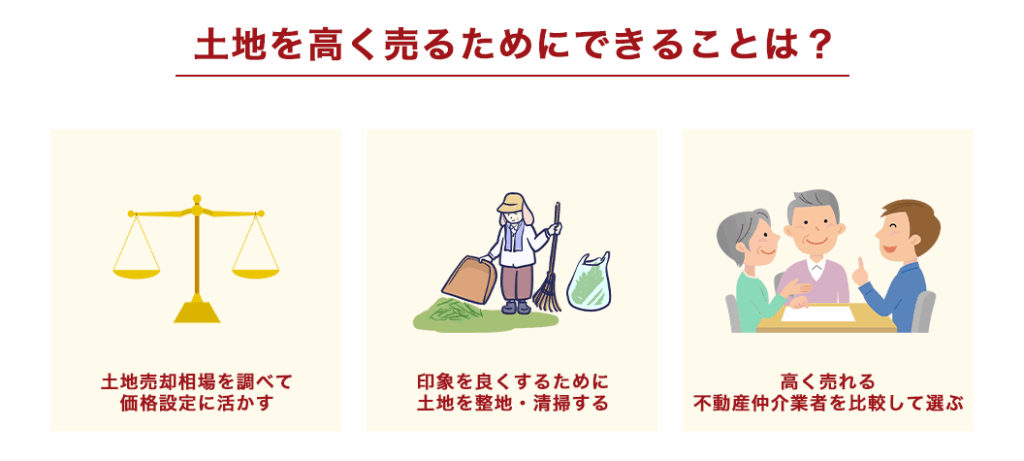
土地は「ただ売る」だけでは本来の価値を発揮できません。
少しの工夫や準備で、売却価格を数十万円〜数百万円単位で引き上げられることもあるのです。
ここでは、土地をできるだけ高く、かつスムーズに売却するための具体的な方法を紹介します。
- 土地売却相場を調べて価格設定に活かす
- 印象を良くするために土地を整地・清掃する
- 高く売れる不動産仲介業者を比較して選ぶ
土地売却相場を調べて価格設定に活かす
適正な売出価格を設定するには、まずは周辺の相場を正しく把握しましょう。
高すぎる価格では買い手がつかず、逆に安すぎれば損をしてしまいます。
土地の相場を調べる主な方法は以下の3つです。
- 国土交通省の「土地総合情報システム」で過去の実売価格を確認する
- 地価公示・地価調査などの公的価格を参照する
- 不動産一括査定サイトで複数の査定額を比較する
実際に市場で売れた価格と、売り出し中の価格には差があることも多いため、「売れた実績ベース」で検討するのが理想的です。
印象を良くするために土地を整地・清掃する
土地の第一印象は、購入希望者の判断に大きく影響します。
雑草が生い茂っていたり、ゴミが放置されている状態では、見た目だけでマイナス評価になり、価格交渉で不利になりやすいのです。
そこで、売却前に次のような整備を行うと効果的です。
- 雑草の除去と簡単な整地
- ゴミ・廃材の撤去
- 看板やフェンスなどの老朽物の処分
- 接道面の見え方をよくする工夫
わずかな清掃でも、「大切に管理されていた土地」という印象を与えることができ、買主の心理的ハードルを下げることにつながります。
高く売れる不動産仲介業者を比較して選ぶ
土地を高値で売却するためには、売却戦略に長けた不動産仲介業者選びが非常に重要です。
不動産仲介業者によって得意とするエリアや客層が異なり、集客力・広告手法・交渉スキルにも差があります。
そのため、最低でも3社程度の査定結果と対応を比較することが推奨されます。
比較する際は、単に提示された査定価格だけでなく、次のような点にも注目しましょう。
- 担当者の説明が明確で信頼できるか
- 売却戦略や販売チャネルの提案が具体的か
- 対応スピードや柔軟性があるか
土地売却でよくある悩みとその解決策
土地売却は不動産取引の中でも高額なため、不安や悩みを抱える方も少なくありません。
ここでは、売却を検討する多くの人がつまずきやすいポイントと、それに対する具体的な対処法を紹介します。
土地がなかなか売れない場合は価格や見せ方を見直す
土地を売り出したものの、「数ヶ月経っても買い手が見つからない」そんな状況は珍しくありません。
その場合、最初に見直すべきは「売出価格」です。
査定価格にこだわりすぎて相場より高めに設定してしまうと、内覧すら入らないこともあります。
また、写真の掲載内容や広告文、現地の見た目(草木の管理や案内板など)も、購買意欲に影響を与えます。
対処法としては以下のようなアプローチが有効です。
- 近隣の成約事例と比較して価格を再検討する
- 広告文や写真を改善し、魅力が伝わるよう工夫する
- 土地の用途や活用イメージを提示する(例:駐車場や戸建て用地など)
客観的に土地の魅力を見せる視点が重要です。
不動産仲介業者と相談のうえ、柔軟な対応を心がけましょう。
ローン残債がある土地でも売却は可能
土地に住宅ローンなどの借入が残っている状態でも、売却は可能です。ただし、注意すべき点がいくつかあります。
基本的には、売却代金からローンを完済しなければ所有権移転登記ができないため、抵当権を抹消できません。
売却代金でローンを返済しきれない場合、自己資金で不足分を補うか、任意売却を検討する必要があります。
スムーズに売却するためのポイントは以下の通りです。
- 現在のローン残高を金融機関に確認する
- 査定額とローンのバランスを見て、売却後の返済可能性を把握する
- 金融機関への事前相談を行い、売却許可(抵当権抹消)を取り付ける
ローンのある土地売却には金融機関との調整が不可欠です。
必要であれば、不動産仲介業者経由での交渉や、専門家のサポートを受けると安心です。
売却後の確定申告は早めに準備するのが安心
土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年の確定申告で申告と納税が必要になります。
申告期限は毎年2月16日〜3月15日で、間に合わないと延滞税などのリスクもあります。
確定申告に備えて、以下の書類は必ず保管しておきましょう。
- 売買契約書(コピー)
- 仲介手数料などの領収書
- 取得費の証明となる書類(購入時の契約書など)
- 登記費用の領収書
また、譲渡所得には特別控除や税率の軽減措置があるため、節税を考慮するなら税理士への相談も検討しましょう。
「売って終わり」ではなく、「売却後の手続きまでが土地売却」であるという意識を持つことが大切です。
失敗しない土地売却のために大切なことまとめ
土地売却は、売却価格の妥当性だけでなく、手続きの正確さや税務処理まで含めた総合的な判断が求められる重要な取引です。
焦って進めたり、手順を省略したことでトラブルになるケースも少なくありません。
後悔のない土地売却を実現するためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
- 事前準備を丁寧に進めること
名義や境界の確認、必要書類の整理など、売却前に行うべき作業を早めに着手しましょう。
特に相続や共有名義の土地は時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールが大切です。 - 不動産仲介業者を慎重に選ぶこと
一括査定などを活用し、複数の会社を比較することで、信頼できるパートナーを見極めることができます。
査定額だけでなく、対応の丁寧さや提案内容も重要な判断基準です。 - 税金や費用を理解し、必要に応じて専門家に相談すること
売却には譲渡所得税や登記費用など様々なコストがかかります。
相続や特例制度に関する知識があると、節税にもつながります。
不安があれば税理士や司法書士など専門家のサポートを受けるのが賢明です。
土地売却は「誰に相談し、どう準備し、どう進めるか」で結果が大きく変わります。
正しい情報をもとに落ち着いて判断し、自分にとって最良の売却を目指しましょう。